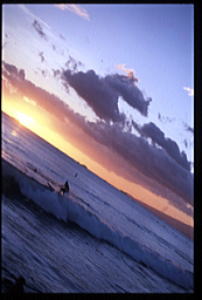 |
「君の名前は?」 「クーチ」 「くーち?」 「そう。本名を思い出せないんだ」 |
||
5歳の時に、 プロのサーファーだった母親が、この海で他界した。 父親が連れてきた新しい家族に、 彼女はどうしても 馴染むことが出来なかった。 |
 |
||
 |
強くて、孤独な瞳の意味 |
||
|
 |
||
口説いてるつもりはなかったが、 クーチは笑い泣きのように顔を歪ませた。 誰かを守りたいと思ったのは、きっとそれが初めてだった。 |
|||
【Next】